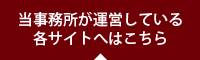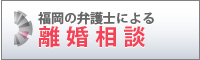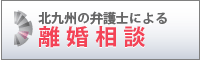訪日外国人の増加に伴う国際結婚・国際離婚
国際結婚・国際離婚の増加の見込み(?)
 昨年の令和元年4月1日から、外国人労働者の受け入れを拡大し、日本国内の労働力不足を解消することを目的として、「特定技能」という新たな在留資格を盛り込んだ改正出入国管理法が施行されています。
昨年の令和元年4月1日から、外国人労働者の受け入れを拡大し、日本国内の労働力不足を解消することを目的として、「特定技能」という新たな在留資格を盛り込んだ改正出入国管理法が施行されています。
これを基に、政府は、5年間で最大34万5000人の外国人労働者を受け入れる計画を立てており、今後、外国人労働者が増加することが見込まれます。
さらに、本年はいよいよ東京オリンピックが開催されますから、外国人観光客の訪日が増加することが見込まれます。
そうすると、(やや唐突ですが)このような外国人の訪日の増加に伴い、日本人と外国人との出会いが増加して、今後、国際結婚をされる方も増えていくのではないかと予想されます。
また、そのコロラリーとして、国際離婚も増えていくのではないかと予想されます。
そこで、国際離婚をせざるを得ないとなった場合に法的に問題となるポイントについて、いくつかご説明をしたいと思います。
国際離婚は、どの国の裁判所で解決するの?――裁判管轄の問題
 国際離婚で、離婚調停や離婚訴訟等の裁判所の手続きを使って解決しようとする場合、どの国の裁判所で解決をすればいいのでしょうか。
国際離婚で、離婚調停や離婚訴訟等の裁判所の手続きを使って解決しようとする場合、どの国の裁判所で解決をすればいいのでしょうか。
すなわち、国際離婚事件の国際裁判管轄は、どの国にあるのでしょうか。
実は、国際離婚事件の国際裁判管轄の決定については、世界共通のルールは存在せず、国ごとの自主的な規律によって決定されているのが現状です。
しかも、この点について、日本の場合は、国内法においても、国際離婚事件の国際裁判管轄の決定について直接定めた明文規定は存在しません。
では、どのように決定されているかというと、以下の判例によって決定されています。
判例 最高裁 昭和39年3月25日 判決
日本の最高裁判所は、訴訟手続上の正義の観点などから、被告の住所地国に国際裁判管轄を認めることを原則としつつ、被告が日本に住所を有しない場合であっても、以下の3つの場合には、公平の観点から例外的に日本に国際裁判管轄を認めるという立場をとることを明らかにしています。
①原告が遺棄された場合
②被告が行方不明である場合
③その他これに準ずる場合
この最高裁判例が出て以降は、実務上も、このルールに従って国際離婚事件の国際裁判管轄が決定されています。
これを具体的にみると、たとえば、日本の方がA国の方と離婚したい場合、A国の方の住所が日本国内にあれば、日本の裁判所に離婚調停・離婚訴訟を提起することができますが、A国の方の住所が外国にあれば、その外国の裁判所に離婚訴訟を提起しなければなりません。
ただし、A国の方の住所が外国にある場合であっても、
①日本の方が遺棄された場合
②A国の方が行方不明である場合
③その他これに準ずる場合 には、
例外的に、日本の裁判所に離婚調停・離婚訴訟を提起することができるようになります。
なお、国際離婚の国際裁判管轄について、詳しくはこちらをご覧ください。
国際離婚は、どの国の法律に従って解決するの?――準拠法の問題
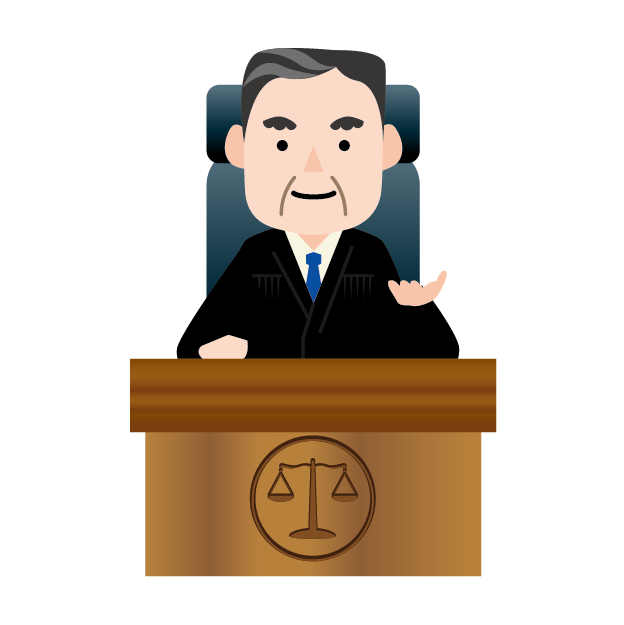 次に、仮に日本の裁判所に管轄がある場合でも、必ずしも日本の法律に従って国際離婚事件を解決するとは限りません。
次に、仮に日本の裁判所に管轄がある場合でも、必ずしも日本の法律に従って国際離婚事件を解決するとは限りません。
国際的な事件についてどの国の法律に従って解決するかという問題を、準拠法の問題といいますが、国際離婚の場合、準拠法はどのように決定されるのでしょうか。
この点については、「法の適用に関する通則法」という日本の法律(以下、「通則法」といいます。)に定めがあり、以下に説明するとおり、離婚の際に問題になる条件ごとに、準拠法の決め方が微妙に異なります。
国際離婚の成立及び効力の準拠法
国際離婚の成立及び効力の準拠法に関して、通則法第27条及び第25条は、以下のとおり定めています。
- 通則法第25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 - 通則法第27条(離婚)
第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
すなわち、通則法第27条本文は、「婚姻の効力」に関する準拠法を規定する通則法第25条を準用していますから、国際離婚の成立及び効力の準拠法については、
①夫婦の本国法が同一であるときはその法律により、
②その法律がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法律により、
③そのいずれの法律もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法律により、
解決されることになります。
ただし、通則法第27条但書は、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」としています。
そうすると、一方当事者が日本に常居所を有する日本人である場合には、相手方の国籍にかかわらず、日本の法律を準拠法として解決することになります。
 これを具体的にみると、たとえば、日本の方がA国の方と離婚したいために日本の裁判所に離婚訴訟を提起した場合、まず、
これを具体的にみると、たとえば、日本の方がA国の方と離婚したいために日本の裁判所に離婚訴訟を提起した場合、まず、
①日本の方が日本に常居所を有していれば、日本の法律を準拠法として解決することができます(通則法第27条但書)。
そうでない場合、このケースですと「夫婦の本国法が同一であるとき」には該当しえませんから、
②夫婦の常居所地法が同一である場合はその国の法律を準拠法とし(「その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により」)、
さらに、③夫婦の常居所地法が同一でない場合は、夫婦に最も密接な関係がある国の法律を準拠法とします(「そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による」)。
なお、ここでいう「夫婦に最も密接な関係がある地」とは、たとえば、別居前に婚姻共同生活血がある場合はその国の法律が、それもない場合は、婚姻地、子どもの居住地、夫婦財産の所在地等の要素を考慮に入れて、夫婦に最も密接な関係がある地を決めることになります。
親権ないし監護権の準拠法
親権ないし監護権の準拠法に関して、通則法第32条は、以下のとおり定めています。
- 通則法第32条(親子間の法律関係)
親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
すなわち、
①子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合はその国の法律
②そうでない場合には、子の常居所地の法律 により解決することになります。
 これを具体的にみると、たとえば、日本の方がA国の方と離婚したいために日本の裁判所に離婚訴訟を提起した場合、
これを具体的にみると、たとえば、日本の方がA国の方と離婚したいために日本の裁判所に離婚訴訟を提起した場合、
①お子さんが日本国籍であれば日本の法律により、
②そうでない場合には、お子さんが常居所として住んでいる国の法律により、
親権ないし監護権の問題を解決することになります。
財産分与の準拠法
財産分与の準拠法に関しては、判例実務は、通則法第27条に従って解決されています。
すなわち、上記(1)の国際離婚の成立及び効力の準拠法の決定方法と全く同じです。
慰謝料の準拠法
 離婚に伴って慰謝料を請求する場合の準拠法は、基本的には、上記(1)の国際離婚の成立及び効力の準拠法の決定方法と同じく、通則法第27条に従って解決されることが多いです。
離婚に伴って慰謝料を請求する場合の準拠法は、基本的には、上記(1)の国際離婚の成立及び効力の準拠法の決定方法と同じく、通則法第27条に従って解決されることが多いです。
ただし、慰謝料の前提事実となる不法行為が、離婚に至る経緯や離婚自体とは関係性の薄い独立した不法行為といえる場合、通則法第17条ないし第22条までの規定に従って準拠法を決定します。
たとえば、通則法第17条は、以下のとおり定め、加害行為の結果発生地や加害行為地の法律を準拠法とすることとしています。
- 通則法第17条
不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、加害行為の結果が発生した地の法による。ただし、その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは、加害行為が行われた地の法による。
婚姻費用・養育費の準拠法
婚姻費用・養育費の準拠法に関しては、扶養義務の準拠法に関する法律がこれを定めています。
扶養義務の準拠法に関する法律
- 第ニ条(準拠法)
- 扶養義務は、扶養権利者の常居所地法によつて定める。ただし、扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によつて定める。
- 前項の規定により適用すべき法によれば扶養権利者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によつて定める。
すなわち、原則として、扶養権利者(養育費請求の場合は、お子さん)の常居所地の法律に従って解決しますが、常居所地法により扶養請求が認められない場合は当事者の共通本国法によって、さらに当事者の共通本国法によっても扶養を受けることができない場合は、 日本法によって、解決することになります。
これを具体的にみると、たとえば、日本の方(母親)が、お子さんと日本在住の上、A国の方と離婚したいために日本の裁判所に離婚訴訟を提起した場合、お母さんもお子さんも日本が常居所地ですので、日本の法律によって婚姻費用・養育費の問題を解決することになります。
なお、準拠法について、詳しくはこちらをご覧ください。
国境を越えて子どもが連れ去られたら、どうすればいい?――いわゆるハーグ条約
 さらに、国際離婚において別居を開始する際など、一方当事者が、国境を越えてお子さんを連れ帰る場合があります。
さらに、国際離婚において別居を開始する際など、一方当事者が、国境を越えてお子さんを連れ帰る場合があります。
この場合、連れ帰った側からすれば、相手方にお子さんを返したくないと考え、反対に残された側からすれば、お子さんを取り返したいと考えるケースが多いため、深刻な争いとなり得ます。
このような、国境を越えたお子さんの取戻し又は取戻しの阻止の問題は、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(いわゆる「ハーグ条約」)という国際条約、及びこれを国内法化した国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(いわゆる「ハーグ条約実施法」)に従って、解決されることになります。
以下、一方配偶者が、外国から日本にお子さんを連れ帰った場合を想定して、ハーグ条約およびハーグ条約実施法のポイントのみご説明します。
この場合、外国に残された他方配偶者としては、日本の外務大臣に対し「外国返還援助の申請」を行ったうえ、日本の東京家庭裁判所又は大阪家庭裁判所に対し「子の返還申立て」をすることになります。
同時に、「子の出国禁止命令及び旅券提出命令の申立て」をすべき場合も多いでしょう。
その後、家庭裁判所においては、「返還拒否事由」の有無が争点となります。
すなわち、返還拒否事由がなければ、お子さんを元の居住国へ返還しなければならず、他方、返還拒否事由が認められれば、基本的にはお子さんの返還をしなくて済むようになります。
具体的な返還拒否事由は、以下の6つです。
- ① 連れ去り又は留置開始の時から1年以上経過した後に裁判所に申立てがされ、かつ、子が新たな環境に適応している場合
- ② 申立人が連れ去り又は留置開始の時に現実に監護の権利を行使していなかった場合(当該連れ去り又は留置がなければ申立人が子に対して現実に監護の権利を行使していたと認められる場合を除く)
- ③ 申立人が連れ去り若しくは留置の開始の前にこれに同意し、又は事後に承諾した場合
- ④ 常居所地国に返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすこと、その他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある場合
- ⑤ 子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において、子が常居所地国に返還されることを拒んでいる場合
- ⑥ 常居所地国に子を返還することが人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められない場合
ハーグ条約について、詳しくはこちらをご覧ください。
国際離婚でお悩みの方は、弊所弁護士にご相談ください
 このように、国際離婚の問題は、国際裁判管轄や準拠法、国際条約等についての深い知識が必要であり、日本国内における離婚問題よりも、一層高い専門性が求められる分野です。
このように、国際離婚の問題は、国際裁判管轄や準拠法、国際条約等についての深い知識が必要であり、日本国内における離婚問題よりも、一層高い専門性が求められる分野です。
弊所は、日本国内における離婚問題は当然のことながら、国際離婚にも力を入れております。
国際離婚でお困りの方は、弊所まで、どうぞお気軽にお問い合わせください。
弁護士コラム バックナンバー
-
 昨年の令和元年4月1日から、外国人労働者の受け入れを拡大し、日本国内の労働力不足を解消することを目的として、「特定技能」という新たな在留資格を盛り込んだ改正出入国管理法が施行されています。 これを基...[続きを読む]
昨年の令和元年4月1日から、外国人労働者の受け入れを拡大し、日本国内の労働力不足を解消することを目的として、「特定技能」という新たな在留資格を盛り込んだ改正出入国管理法が施行されています。 これを基...[続きを読む]