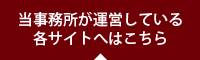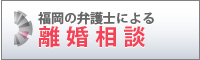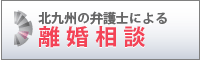子の返還を拒める場合(ハーグ条約実施法)
 ハーグ条約の実施法28条1項に規定されています。
ハーグ条約の実施法28条1項に規定されています。
ハーグ条約の実施法(以下では「実施法」と略します。)の28条1項には、返還拒否事由として6種類が定められています。
以下の6つの要件に1つでも該当する場合は、子どもを常居所地国に返還することを拒否できます。
- 返還申立てが、連れ去りのとき又は留置の開始時から1年を経過した後にされ、かつ、子が新たな環境に適応していること
- 申立人(残された親)が、連れ去りのとき又は留置の開始時に、子に対して現実に監護の権利を行使していなかったこと
- 申立人が、連れ去りの前もしくは留置の開始の前にこれに同意し、又は、連れ去り後もしくは留置の開始後にこれを承諾したこと
- 常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子を堪え難い状況に置くこととなる重大な危険があること
※残された親が、子を虐待したり、連れ帰った親にDVを行っていたりした場合については、こちらをご覧ください。 - 子が常居所地国に返還されることを拒否していること
※ 子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当な場合に限られます。 - 常居所地国に子を返還することが日本国における人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められないものであること
実施法28条1項1号
子の返還の申立てが当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時から一年を経過した後になされたものであり、かつ、子が新たな環境に適応していること
ハーグ条約及び実施法は、連れ去りや留置によって子の環境が大きく変化することは、子の成長に重大な影響を及ぼしてしまうため、一日でも早くもとの環境に戻すということを目的としています。
連れ去りや留置から一年を経過した場合は、子が新たな環境に適応してくるとみられるため、返還拒否ができるものと定められています。
ただし、1号に該当すると判断されたとしても、もとの国に子を戻すことが子の利益にかなうと判断された場合は、やはり子を返還しなければなりませんので注意が必要です(実施法28条1項ただし書き)。
なお、連れ去り又は留置の開始時から子の返還申立てまでの間に一年を経過しているかどうかは客観的に明らかであることがほとんどであるため、1号に基づく拒否事由があるとされた例はいまのところありません。
一方、連れ去りをした親側の反論で、一年未満であるものの、1号が適用されるべきだ(法律上はこれを類推適用といいます。)と主張された例はあるようですが、連れ去りをされた親の監護権が侵害されているにもかかわらず返還を拒むに足りる最低限の期間として一年を要するというのが法の趣旨であるという理由で、裁判所は上記の主張を認めませんでした。
実施法28条1項2号
申立人が当該連れ去りの時又は当該留置の開始の時に子に対して現実に監護の権利を行使していなかったこと(当該連れ去り又は留置がなければ申立人が子に対して現実に監護の権利を行使していたと認められる場合を除く。)
返還を申し立てることができるのは、連れ去り又は留置によって、「監護の権利を侵害された者」とされています(実施法26条)。
そのため、監護権をそもそも行使していなかった場合は、その権利の侵害が考えられないため、返還を拒むことができます。
ただし、1号と同様で、2号に該当する場合でも子の利益に資すると裁判所が判断すれば、子を返還する命令が出されるので注意が必要です。
2号については、連れ去り又は留置をされた親が監護権を有しているにも関わらず、これを行使していなかったという事態があまり生じない(少なくとも申立てがなされて裁判所にあがってくるものとしては。)ため、主張されることはあまりないというのが実体です。
なお、海外では、現地の裁判所の判断がない限り、原則として監護権はあるものと考えます。
逆にいえば、連れ去り又は留置をした親に単独の監護権を認める判断がないのであれば、2号の主張は認められないと考えるべきです。
残された親がまったく子の面倒を見ずに放置してどこかに行っていたということが立証できれば(例えば、子はずっとA国にいたが、残された親(返還を求める親)はその間B国にずっといたというのがパスポートの履歴から明らかであるなど)ある程度反論もできるでしょうが、同じ国内の違う場所にいた程度の話であれば、立証は難しいでしょう。
また、「子に対する関心が希薄だった。」「子にDVをしていた。」といった理由で2号の主張をすることを裁判所は認めていません。
これは、監護者として適格であるかどうかの問題であって、不適格な状況が見受けられたとしても、それをもって監護権の不行使であると意味するものではないと裁判所が考えているためです。
厳しい見方ではありますが、実施法に基づく手続きが監護の適格性を判断する場ではない以上、裁判所の考え方がおかしいとまではいえません。
実施法28条1項3号
申立人が当該連れ去りの前若しくは当該留置の開始の前にこれに同意し、又は当該連れ去りの後若しくは当該留置の開始の後にこれを承諾したこと
連れ去り又は留置をされた親が、事前または事後にそれを同意したのであれば、その親は、子が新しい環境に置かれることを受け入れた(acceptance of the new situation)ということになるため、返還拒否事由とされています。
ここで定める「同意」の内容ですが、子を連れて外国から日本に入国した場合を例にすると、外国に住む親が、子が一時的に日本に滞在するにとどまらず、その後も日本に相当長期間にわたって居住し続けることまで同意又は承諾し、もはや子の返還を求める権利を放棄したといえることが必要であるとするのが日本の裁判所の考え方です。
同意があったか否かについては、他の規定に比べて争点にされやすい部分です。
多い例としては、同意を示すメールなどが証拠として提出されるような場合ですが、当事者間で意見の変遷が生じることもよくあることから、出国の前後の状況を主張・立証の必要があります。
以下では、相手の配偶者を置いて、自分が子を連れて出国したケースを例に見ていきます。
自分が子を連れて出国したケース
出国時について
まず何よりも、帰国時に連れ去り又は留置をされる親の同意があったことを示す資料が必要です。
争いになるのは、この資料が裁判所の命令といったものではなく、メールのみといった場合です。
「口頭で同意を得た。」という程度では、相手は「そんな同意はしていない。」と主張するだけで、実際どうだったのか客観的に立証ができないため、返還を拒むことが難しくなります。
出国前について
次に、帰国前の当事者間のやり取りに着目します。以下ではいくつか例を挙げます。
 帰国のチケットの購入状況
帰国のチケットの購入状況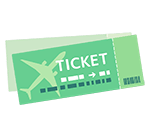 チケットを購入したのが、連れ去り等をされたと主張する親だった場合、そのチケットが往復券であれば、連れ去り等の同意をしていないと評価されます。
チケットを購入したのが、連れ去り等をされたと主張する親だった場合、そのチケットが往復券であれば、連れ去り等の同意をしていないと評価されます。
往復券の場合は、子と一緒に戻ってきてほしい(=相当長期間にわたっての居住を容認していたのであれば、帰りのチケットを購入することはない)と考えているといえるからです。
一方、購入したチケットが片道のものであれば、もとの居住地に帰国することを予定していない、そのような状況を容認している、と評価されますので、連れ去り等の同意をしたものと評価されます。
ただし、「一時帰国をするだけだと思っていた。」と主張されることもあり、現に過去にも一時帰国を繰り返していたといった状況にあった場合は、「相当長期間にわたって居住し続けることまでの同意」をしたとはいえなくなるため、このときは同意をしていないと評価されてしまいます。
他方、子を連れ去り等した親が片道チケットを購入した場合ですが、その親が「帰国するつもりはない」という意思表明であることは確かであるものの、連れ去り等をされた親が帰国を同意又は承諾したかどうかとは別問題です。
もちろん、同意があったからこそ帰国を決行したわけなので、連れ去り等をした親の行動として矛盾しない事実の一つではありますが、それだけで同意が得られたと評価することは難しく、あくまで周辺事情にとどまるでしょう。
 子の身辺整理の状況
子の身辺整理の状況 まず、子が海外で幼稚園などに通っている場合、もしもとの居住地に帰国をするつもりがないのであれば、連れ去り等を行う親は、退園手続きをとったり、他の園児とのお別れ会(又はその挨拶)などをしたりするのが通常と考えられます。
まず、子が海外で幼稚園などに通っている場合、もしもとの居住地に帰国をするつもりがないのであれば、連れ去り等を行う親は、退園手続きをとったり、他の園児とのお別れ会(又はその挨拶)などをしたりするのが通常と考えられます。
そのため、そのようなことをしていなかった場合は、同意を得たと主張する親の行動としては矛盾したもの(=同意は得られていなかったのではないか)との評価を受けてしまいます。
他方、そのようなことをしていた場合、同意を得たと主張する親の行動としては矛盾しない事実と評価されます。
ただし、前述と同様、連れ去り等をされた親の同意があったかどうかとは別問題であるため、あくまで周辺事情にとどまります。
次に、子に必要な洋服やおもちゃ、手続書類(母子手帳や保険証類)などについて、それらは出国先の生活で必要になるものなので、もとの居住地に帰国する意思がなければ、通常は持ち帰るものです。
そのため、そのようなことをしていなかった場合は、前記と同様に、同意を得たと主張する親の行動としては矛盾したもの(=同意は得られていなかったのではないか)との評価を受けてしまいます。
他方、そのようなことをしていた場合、同意を得たと主張する親の行動としては矛盾しない事実と評価されますが、この点も前述と同様、連れ去り等をされた親の同意があったかどうかとは別問題であるため、あくまで周辺事情にとどまります。
 連れ去り等をされた親の言動
連れ去り等をされた親の言動子の返還を求める意思を表明していた場合、それは相当長期にわたって他国に居住することを認めない言動といえるため、同意がなかったものと評価されます。
 日本では、妻が子を連れて別居を開始したとしても「連れ去り」と評価されることはほぼありません。
日本では、妻が子を連れて別居を開始したとしても「連れ去り」と評価されることはほぼありません。
しかし、海外の場合、親の子に対する権利は父母で厳格に平等とされることがほとんどです。
そのため、国境を越えた別居を実行するには、裁判所の命令で単独監護権を取得しておくべきだといえます。ですので、まずは必ず現地の弁護士に相談をしてください。
出国後について
そして、帰国後の当事者間のやり取りに着目します。
 連れ去り等をされた親が、出国先での子の滞在が当事者間で当初予定された期間を超過し、残された親が滞在の延長について同意又は承諾した場合
連れ去り等をされた親が、出国先での子の滞在が当事者間で当初予定された期間を超過し、残された親が滞在の延長について同意又は承諾した場合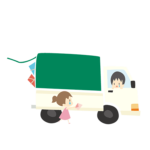 従前から子の返還を求める意思を表明していれば、相当長期にわたる居住は認めていないということになりますので、同意はなかったと評価されます。
従前から子の返還を求める意思を表明していれば、相当長期にわたる居住は認めていないということになりますので、同意はなかったと評価されます。
そのため、一時的に出国することができたとしても、結局は裁判所による返還命令が出される可能性が残ります。
 連れ去り等をされた親が、出国先で滞在するために必要な協力をしていた場合
連れ去り等をされた親が、出国先で滞在するために必要な協力をしていた場合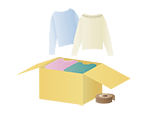 具体的には、子の住居や転学・転園先の確保に必要な諸手続きや、出国後に、残置していた子の身の回りの物品を送付するような行為が挙げられます。
具体的には、子の住居や転学・転園先の確保に必要な諸手続きや、出国後に、残置していた子の身の回りの物品を送付するような行為が挙げられます。
これは、どの程度の協力があったかによって評価がわかれます。協力行為によって、もはやもとの国で生活することはなく、出国先で相当長期の居住に必要な協力として行われたといえれば、同意があったものと評価されることになります。
他方、子の返還に向けた準備行為、具体的には、子の帰国時期の調整、復路の航空券の手配、もとの国での国での復学等の申し込みなどが行われた場合は、出国先での相当長期にわたる居住とは矛盾する行為なので、同意はなかったと評価されます。
実施法28条1項4号
常居所地国に子を返還することによって、子の心身に害悪を及ぼすことその他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険があること
4号の文言は上記のとおりです。「常居所地国」の定義は実施法2条5号に記載されていますが、わかりやすくいえばもともと住んでいた国のことです。
さらに、実施法28条2項には、この4号該当性の考慮事情を記載しています。
実施法28条2項
一 常居所地国において子が申立人から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次号において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無
二 相手方及び子が常居所地国に入国した場合に相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無
三 申立人又は相手方が常居所地国において子を監護することが困難な事情の有無
以下順に上の3つの考慮事情についてみていきます。
考慮事情
 子が申立人から身体に対する暴力等を受けるおそれの有無
子が申立人から身体に対する暴力等を受けるおそれの有無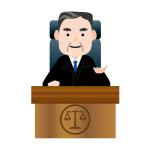 ここでいう「おそれ」については、過去に行われた暴力等の事実が認定され、それに基づいてどの程度「おそれ」があるかを推認するという方法で判断されます。
ここでいう「おそれ」については、過去に行われた暴力等の事実が認定され、それに基づいてどの程度「おそれ」があるかを推認するという方法で判断されます。
では、過去の暴力等の有無についてはどのように認定されるのでしょうか。
■裁判所は、連れ去り等を行った親の供述だけで過去の暴力等を認定することには慎重な姿勢を持っている。
つまり、客観的な証拠資料がない限り、過去に暴力等があったとは認定されないのが実情です。
客観的な資料の具体的な例としては、暴力によって受けた怪我を治療した診断書でしょう。
その他には、常居所地国における生活中に、すでに児童福祉機関の関与があった場合、その期間による調査報告の内容が資料として挙げられます。
ただ、そのような資料が提出されるケースはあまり多くはないようで、実際は、過去の暴力等をうかがわせる写真やメール、警察等への通報記録等と言ったものが多いのが実体です。
実際に裁判手続きで提出された資料として、返還を求める親の暴力等があることを前提として、子にフラッシュバックの症状や心的外傷後ストレス障害が生じているという診断書があります。
連れ去り等をした親としては、この証拠をもって、過去に暴力行為があったことを立証しようとしたものです。
しかし、裁判所は、診断書が、連れ去り等をした親の説明に基づく説明で、その内容の正確性が必ずしも担保されていなかったことや、子の返還手続きにおける資料として利用することを当初から意図して作成されていたことなどを理由に、暴力の事実を認定しませんでした。
以上をみると、暴力等がなされた場合は、病院へ行くことはもちろん、現地の児童相談所、警察などの公的機関に相談し動いてもらうこと、それがわかる資料をもらっておくなどしておく必要があります。
■裁判所は、一定の強度の暴力等があったとして、それが継続的又は恒常的に行われていたことが必要と判断する傾向にある。
これは、病院への受診歴や、受診時の怪我の状況・程度から、度重なる暴力等があったことを立証することになるところです。
他方、以下のような程度では、継続的又は恒常的に暴力等が行われていたとは判断されません。
- 連れ去り等をした親や子の不注意を叱る際に声を荒げることがあった
- 飲酒の際に時折大声を出すことがあった
- しつけとして子の臀部等を叩くことがあった
- 連れ去り等をした親の頬を平手ではたいたことが数回あった
また、返還を求める親が、子からの要望を無視していたという事情は、それが子の成長過程において甘受すべき不便や不自由の域を出ないものであれば、ネグレクトと評価できないと判断されています。
 相手方が、申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無
相手方が、申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受けるおそれの有無 この規定は、連れ去り等をしたとされる親への暴力が、子の面前でなされていた場合のことを想定しています。
この規定は、連れ去り等をしたとされる親への暴力が、子の面前でなされていた場合のことを想定しています。
ここでいう暴力は子が心的外傷を受けるほどのものでなければならないとされており、子の認識できる状況下で暴力等がなされたということを立証しなければなりません。
具体的には、親が暴力等を受けた際に、子が仲裁に入る声が録音されていたり、泣き声が録音されていたりといったものが考えられます。
ただ、そういった状況下での録音は現実的に困難であるケースが多いと思われます。
以上をみると、親の暴力が、子に直接向けられていない点で立証の難易度が上がっているといえます。
 申立人又は相手方が常居所地国において子を監護することが困難な事情の有無
申立人又は相手方が常居所地国において子を監護することが困難な事情の有無「困難な事情」の判断をする際は、以下の事情が考慮されます。
- 常居所地国における滞在資格及びその取得の可能性
- 稼働意欲・稼働能力の有無・程度
- 就職先・子の通学先等の確保の可能性、家族・友人・支援機関から受けられる援助の有無・程度
- アルコールや薬物依存症・精神疾患といった心身の健康上の問題の有無・程度
 連れ去り等をした親からは、子の返還が必然的に自身と子の分離を意味するため、常居所地国で生活をさせることは子を耐え難い状態に置くという主張がなされることがあります。
連れ去り等をした親からは、子の返還が必然的に自身と子の分離を意味するため、常居所地国で生活をさせることは子を耐え難い状態に置くという主張がなされることがあります。
この主張を維持するのであれば、連れ去り等の行為が、常居所地国では刑事訴追を受けることが不可避であることが客観的に明らかであるとか、常居所地国で十分な生活をしていけるだけの支援がおよそ期待できない事情、あるいは、深刻なDV被害を受けるために連れ去り等をした親が自殺や自傷に及ぶ危険性があるという裏付け資料が必要になります。
また、仮に、連れ去り等をした親と子が離れることになったとしても、国境を隔てた状況での面会交流が実施されるのであれば、子が受ける精神的負担は限定的であるとして、子が耐え難い状況にはおかれるわけではないと判断される可能性があります。
実施法の規定は子を常居所地国に返還することを前提としているため、暴力等についてそれが実際に行われていたとしても、それを客観的に立証できる十分な資料がなければやはり返還命令が出てしまいます。
- 暴力が子に直接向けられたものかどうか
- その暴力が継続的、恒常的になされたものか
- それを裏付ける資料が得られていえるか
以上を確認することが重要になります。
※残された親が、子を虐待したり、連れ帰った親にDVを行っていたりした場合については、こちらをご覧ください。
実施法28条1項5号
子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において、子が常居所地国に返還されることを拒んでいること
連れ去りや留置(以下では「連れ去り等」といいます。)をした親は、子が常居所地国に帰国することを望んでいないと考えており、子も親の考えに同調していることが多いため、この5号が争点になることが多いといわれています。
調査官による調査の実施
 5号該当性が主張された場合、基本的には家庭裁判所調査官による調査が実施されることになります。
5号該当性が主張された場合、基本的には家庭裁判所調査官による調査が実施されることになります。
- 子の現状認識
- 常居所地国に帰国することについての子の意見の内容
- 子がそうした意見を持つに至った理由
以上を踏まえて、子がその意見を考慮に入れることが適当な年齢及び成熟度に達しているか、ひいては子の意見が常居所地国に返還されることに対する異議を唱えているといえるかが判断されます。
子の年齢
子の成長は個人差があるため一概にはいえないところがあります。もっとも、裁判所は、
- 子が6歳未満の未就学児童について、子の意向を考慮することが適当とした例はない
- 6歳以上10歳未満の子については、子の意向を考慮することが適当であるとした例はあるものの多くはない
- 10歳以上になると、子の意向を考慮することが適当であるとした例が比較的多い、ただし、子の発達の程度に照らし、10歳以上でも子の意向を考慮することが適当とは言い難いとされた例もある
というのが現状です。
以上を踏まえると、子がおおむね10歳に達しているかどうかが基準になっているようです。
子の発達の程度
子の発達の程度をみる際には、以下が考慮されています。
- 調査時の子の回答内容や態度
- 当事者から提出されたこの学校での成績表その他の資料
また、子に問われているのはあくまで「常居所地国に戻ることについての意見」であり「連れ去り等を行った親と、それをされた方の親と、どちらと暮らしたいか」ではないとされています。
さらに、以下も考慮されています。
- 「常居所地国に戻ること≠連れ去り等をした親と引き離されること」を理解できているのか
- 連れ去り等をした親やその親族の意向とは区別された自分の意思を自身の生活体験に基づいて回答できているか
- 中長期的な観点に基づき常居所地国に戻った場合と日本にとどまった場合とのメリット・デメリットを比較検討したうえで常居所地国に戻りたくない理由を具体的に説明できているか
ここまでみると、返還を拒否することが容認されるだけの子の意見というのは、かなり高度な判断能力に基づくものが必要であることがわかります。
そのため、例えば子が、常居所地国に返還されると、連れ去り等をした親との同居を継続できなくなることへの抽象的な不安や懸念しか述べていない場合は、返還を拒否する意見を表明したものとは評価されない傾向にあります。
子の意見を書いた手紙について
常居所地への返還を拒む場合、子が作成した手紙が証拠資料として提出されることがあります。
これが、適切に子の意見を自らの考えで反映させたものといえるかどうかについては、手紙の作成時期や内容に照らし、連れ去り等を行った親やその親族の影響を受けていないかが検討されます。
具体的にいうと、子の返還の申立てがあったあとに作成されたものであれば、返還を拒む親の意向が反映されていると評価される可能性があります。
また、調査官による聞き取りの際に、子が「●●に帰らない方がいいと言われている」という発言があると、同様に返還を拒む親の意向が反映されていると評価されるといえます。
以上の評価は、結果的に、子が自発的に判断していないという結論を導いてしまうため、証拠提出の際には注意が必要といえます。
実施法28条1項6号
常居所地国に子を返還することが日本国における人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められないものであること
文言だけみてもよくわからない条文ですが、例えば、子がかつて住んでいた国が、基本的人権や自由を不当に制限する法制度を採用している場合や、激しい内戦状態にあって法秩序が保たれていないような場合等が当たるとされています。
6号に該当する場合は、先に見た1号と2号と違い、子をもとの国に戻すことが子の利益に資するとは考えられないことは明らかですので、裁判所が返還命令を出すことはできません。
この規定は非常に特殊な事情下にある住環境であった場合が想定されていますので、実際はこの6号に基づく拒否が認められることはほとんどありません。
まとめ
ここまで、子の意見を考慮する場合の考慮要素をみてきました。
裁判所に返還拒否が認められるためには、以下を冷静に判断できるかが重要です。
- 子が10歳以上であること
- 常居所地国へ戻るか否かについて、メリット・デメリットを自分で考えることができるか
別居を開始するに至った理由は夫婦によりさまざまですし、内容によっては子に言いにくい、説明しにくいことはあると思います。
しかし、いつまでもごまかすことはできません。
夫婦関係の問題について子に責任はありませんので、日ごろから子に対する状況の説明や、子の考えを聞く姿勢を持っておくことが大切です。
 実施法は申立てから原則6週間以内に結論を導く迅速な手続きとされています。
実施法は申立てから原則6週間以内に結論を導く迅速な手続きとされています。
そのため、返還拒否事由の解釈は厳格です。
上記にみたものは返還拒否事由のなかでも特に厳格に解釈されるものです。
1、2、6号での主張を行う場合は、客観性のかなり高い証拠があるか、特殊な(危険な)情勢にある国のときに限られると考えておく必要があります。
もっとハーグ条約について知りたい方はこちら
| ●ハーグ条約とは | ●外国にお子さんを連れ去られてしまった方 |
| ●外国から日本にお子さんを連れ帰った方 | ●子どもを返還しなければならない場合 |
| ●ハーグ条約による援助 | ●管轄裁判所 |
| ●返還申立事件の流れ | ●返還を拒否できる場合 |
| ●残された親からの虐待・DVがある場合 |